2025 年(令和 7 年)は、改正育児・介護休業法が 4 月 1 日、10 月 1 日の 2 度にわたって段階的に施行されます。今回はこの法改正の概要について、分かりやすく解説します。さらに、「いつまでに、どのような準備をすれば良いか」といった、事業主の方、及び人事労務担当者の方々にとって必須となる対応ポイントをみていきましょう。
まず、今回の記事では育児休業など子育て中の従業員に関する制度改正について、解説していきます。介護休業の制度改正については、次回の記事でみていきましょう。
育児・介護休業法の目的は?
育児・介護休業法の正式名称は「育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。文字通り、育児や介護の問題に直面する労働者の福祉向上を目的とするもので、ワーク・ライフ・バランスの実現に寄与するものです。「仕事と育児」、「仕事と介護」の両立を支援することが、育児・介護休業法(以下「育介法」とします)の主な目的です。
今回の法改正では、この「両立」の実現のための施策が大幅に拡充されました。
2025(令和 7)年 4 月 1 日の施行の改正育介法
今回の法改正では、多くの項目で新たに義務化、もしくは努力義務化されています。特に義務化された項目については、就業規則の変更、労使協定の再締結等の対策が必要になりますので、早めの準備をおすすめします。具体的な改正内容は以下の表のとおりです。
ここでは、こちらの 9 項目から、法改正により義務化された項目についてピックアップしてご紹介いたします。
改正育介法によって義務化されるものは?(育児休業、他)
今回の記事では育児休業をはじめとする子育て中の従業員に関する制度改正について、解説していきます。
(介護休業の制度改正につきましては、次回記事をご参照ください。)
1.子の看護休暇の範囲が拡大
子の看護休暇は主に以下3点の改正が行われます。
<改正項目>
対象年齢:小学校就学まで→小学校三年生まで
取得事由:学級閉鎖、学校行事も含める
名称変更:子の看護“等”休暇
事業主の皆さまは、就業規則の改正が必須となります。
(引用:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf)
2.所定外労働の制限を請求できる労働者の範囲が拡大
所定外労働の制限を請求できる労働者の範囲が、「3 歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大されます。
事業主の皆さまは、就業規則の改正が必須となります。
(引用:厚生労働省 PDF リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf)
3.育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業の範囲が拡大
育児休業取得状況の公表義務の対象となる企業の範囲が拡大されます。
これまでは従業員数 1,000 名超の企業に公表義務がありましたが、施工後は従業員数 300 人超の企業から公表義務が発生します。
対象となる企業における事業主の皆さまは、従業員の育休取得状況についての所定の項目を
HP 等で公開することが必須となります。
(引用:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf)
詳細については、厚生労働省のリーフレットも併せてご確認ください
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
さくら労務では、育児介護休業等に関する就業規則や社内規程の
見直しはもちろんのこと労働基準監督署への届出にも対応しております。
(育児介護の労使協定は届出不要です)
まずはお気軽にお問い合わせを!
お問い合わせはこちら


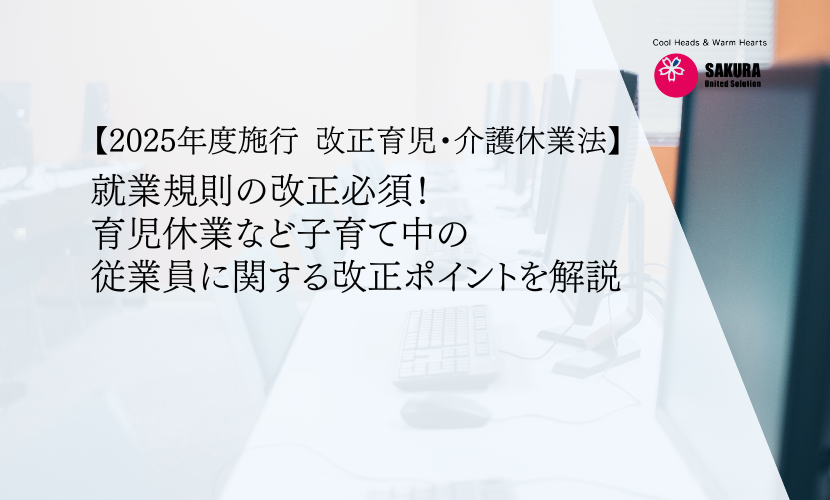
.png)